こちらの短期連載では、映画『街の上で』のプロデューサー髭野純さんを軸に、同世代の若手映画プロデューサーに「これからの映画作り」や「映画を取り巻く環境のこと」などについてお話を聞いていきます。第2回目は、サン・セバスティアン国際映画祭でニュー・ディレクターズ部門に選出され、ポレポレ東中野では3ヵ月のロングランヒットをしている『海辺の彼女たち』のプロデューサー、渡邉一孝さんとの対談インタビューです。
ーー第二回目のゲストは髭野さんからのリクエストで渡邉さんに決まりました。なぜ今回渡邉さんと対談したいと思ったのでしょうか?
髭野純(以下、髭野) 渡邉さんとお話したいと思ったのは、新しいことにチャレンジされている方だからです。社会的な題材を扱い、国際的にも評価される作品を手がけている若手のプロデューサーってすごく貴重だと思います。作品を企画するに至った経緯や、自主配給も務められているので、映画の広げ方、映画祭と上映の進め方などについて話せたらなと。
ーー渡邉さんは、髭野さんに対してどのような印象がありましたか?
渡邉一孝(以下、渡邉) 髭野さんは『太陽を掴め』の頃から知っていました。その頃はたぶんまだお会いしていなかったのですが、脱サラして、自己資金をつぎ込んで、あまり経験の無い監督と一緒に映画作って、テアトル新宿で上映して・・・。その話を聞いたときに、この動き方ってあまりできないなって思ったんです。そしてその姿勢や無謀さみたいなところに共振するもの、共感するものがありました。
ーー第一回目の記事で、髭野さんが海外映画祭についてお話していました。今回はその辺りのお話も深堀してお聞きできればと思います。まず、海外映画祭への出品が大事な理由についてお伺いしたいです。
髭野 映画祭に辿り着く方法っていろいろあると思うんですけど、海外でプレミアをを狙うこと自体ハードルがあるというか、戦略的にやらないとそう簡単にいけないですよね。長編2本目までしか出せない映画祭もあるので、何本も作っているとその時点で参加できなくなってしまうケースもある。やっぱり長編1本目2本目での評価は大事ですよね。その中で、藤元明緒監督の長編第二作である『海辺の彼女たち』がサン・セバスティアン国際映画祭でワールドプレミアされたのは素晴らしいなと思いました。
渡邉 サン・セバスティアン国際映画祭は、『僕の帰る場所』が大きなきっかけでした。『僕の帰る場所』が33の映画祭で上映されたのですが、その中で参加した映画祭での出会いから次の目的地が見えて来たり、繋がりができて今回のワールドプレミアにつながったんだと思います。僕らはなるべく自分たちで直接映画祭にアプローチすることを考えていますね。
髭野 渡邉さんは、いつもどうやって映画祭窓口に辿り着いているんですか?
渡邉 連絡がくることもあれば、自分でエントリーする映画祭もあります。でも、一度やったことがある人はわかると思いますが、自分でエントリーする場合は打率がだいぶ低い…。ワールドプレミアした映画祭をスタートに、どれくらいフェスティバルサーキット(映画祭の上映が続いていくこと)が続いていくか。最初の映画祭がとても大事ですね。
髭野 やっぱりある程度の流れが無いと難しいんですね。
ーー「流れ」とはどういうことでしょうか?
渡邉 業界評やプログラマー評のことです。例えば、『僕の帰る場所』の場合は、僕らが東京国際映画祭の「アジアの未来部門」で二冠とっていることを、知っている人は勉強していて、それを知っているんですよ。サン・セバスティアン国際映画祭の新人監督部門にはこれまで6人しか入っていなかったり、日本とベトナムの共同製作映画もあまりないので、入選したら、ラインナップをチェックしているセールスエージェントから連絡がくるんです。ちゃんと業界のニュースを追ってビジネスをしている人たちは、映画祭を含めていろいろ勉強しているので、その作品を観ておかないとってなる。
映画祭に関しては、自分たちの映画祭にふさわしいと思えば、映画を観たい、と直接連絡してくるんです。フェスティバルサーキットは電車の駅に例えられたりしますが、最初の駅を間違えなければ、その列車を絶対に見ている人がいるから、それが流れになるのだと思います。あと、ライターやジャーナリストの方も常に情報をアップデートしているので、この作品は観ておかなきゃとか、この作品はレビューを書くぞって広がっていって、それがまた流れになるんですよね。

©2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
ーーなるほど。勉強しているライターやジャーナリストの方は映画祭の流れもちゃんと追っているんですね。
渡邉 よく知っている人はそれを加味して、次にこれが来るんじゃないかって見ていると思います。一般的にも、よく起きる流れよりも「ん?なにこれ?」という作品にみんな注目するじゃないですか。流れをよく知る人は、誰が作っているかもそうですが、企画の特殊性だったり、こういった題材はあまりないけどどうなんだろう、と作品に食いつくことも多いと思います。
ーー日本国内でも見ている人は見ているし、追っている人は追っている感じなんですかね?
渡邉 僕らが受賞した「アジアの未来部門」での二冠は“日本人監督作品としては史上初”だったんですけど、あまり知られていない印象です。そういう意味では、「ん?なにこれ」という流れを追っている人はあまり多くないのかもしれません。そういった人たちがもっと多くいて、ジャーナリズムを含め機能していたら、僕らはもっと前作で認知されていたと思います。映画祭や賞などって、ラインナップされた人や作品を知名度が無い所から価値をグッと持ち上げるポンプのような役割があるはずなので、そのポンプがもっとうまく機能してほしいです。
ーーそれは、メディアのニュースとしての取り上げ方も含めてですか?
渡邉 作品が良いからとか、業界的に珍しい動きで注目すべきだから、という理由ではニュースにはなりにくいようです。
髭野 国内の評価と海外での評価が乖離をしていると感じる時があります。もっと国際基準で盛り上がるといいんですけどね。
渡邉 国内のメディアが取り扱う基準が違うというだけだと思うんです。全員が全員取り上げてほしいとかは無いですけど、東京国際映画祭で二冠を受賞したときに、もうちょっと何かが起きてほしかったなという気持ちはありました。
ーー企画段階から、流れを作ることを考えて進めている感じですか?
渡邉 そうですね。あと、1、2、3作目の初期作は監督のアイデンティティになるので、そこまでは自分たちのスタンスというか骨太な部分は守らなければいけないと思っています。それ以降であれば、仕事として映画の長編を撮っても良いけど、そこまでは頑張ろうと。そういう話はよく監督としていますね。1、2があっての3なんだねというようなものは、必然的にやらなければいけないよねと。
サン・セバスティアン国際映画祭では、「E.x.N(エクスン)」という自分の会社で、映画を1本買い付けたんです。それも1、2、3と映画を作っていくなかで、その場である映画と出会って、この映画を配給する理由を感じたので。世の中は変わっていくからわからないけれど、僕らがやっていった先に、これもやらなきゃなっていうものが買付や配給だったり、海外営業だったりするという自然な流れを大事にしたいですね。
ーー髭野さんは今お話を聞いていてどんなことを考えていましたか?
髭野 すごいなと。日本国内でも海外セールスをしてくれる会社ってあると思うんですけど、既に海外の会社に直接預けていたりするということも、今そこまでやれる人はなかなか居ないなって思います。特に独立系の作品だと、マーケットを広げるためにも海外映画祭は重要だと思うんですけど、なかなかそこまでできる人が居ないという感じなので。
ーーお二人はプロデューサーであると同時に配給業も行っています。プロデュースと配給を一緒に行うことの良さはありますか?
渡邉 配給を自分でやると映画館さんとお客さんとの距離が近くなるので、映画を届ける中での一番大事なコミュニケーションを自分で担えるのがいいところですね。「お客さんってどんな人が来ていました?」って、自ら劇場に電話をかけて聞くことができるので。あと、配給は拡大タイミングが奥深いなと思っています。時代の情勢もあるし、狙うタミングもあれば、みんなの期待するタイミングもあるし。映画を作って、最初から最後までやるとなったら、配給も自社で行うというのは考えるべき選択肢だなと感じます。

(C)「街の上で」フィルムパートナーズ
ーー『街の上で』も戦略的に劇場を開けていた印象があります。今後独立系の作品がある一定の規模を越えていくには、やはりシネコンやチェーンでの上映も考えていくことが大事になってくると思うのですが、その辺りお二人はどうお考えでしょうか?
渡邉 昨年から今年にかけて公開された『佐々木、イン、マイマイン』『ミセス・ノイズィ』『街の上で』は、インディペンデント作品のなかでもシネコンで上映された珍しい作品じゃないですか。そういう作品がいくつか出てきているということは、今後も出てくると思っているんです。そして、インディペンデント映画をビジネスとして考えるんだったら、向かっていくべきところの1つだと考えています。
髭野 映画って1800円で、ミニシアターでの1回の上映が10人や5人のときもあるじゃないですか。それが続いた場合経営が成り立たなくなってくるので、映画ってビジネス形態としてすごく難しいですよね。ちなみに渡邉さんは、なぜ「映画」だったんですか?
渡邉 これはよく聞かれるんですけど、別に僕は映画じゃなくてもいいと思ってるんです。映画は好きなんですけど、無くても死なないくらいなので。映画の何が良いかというと、社会のなかで、自分ではない誰か、自分の知らないどこかを体感するのにとても効率のいいメディアだと思っています。『僕の帰る場所』も『海辺の彼女たち』も、いずれも日本にいる外国の方を主人公にしていますが、登場人物の心のなかを追体験することができて、それはニュースでもコラムでもできなくて。小説ではできるのかもしれないけど、
あとは、自分の人生を振り返ると、自分の理想とか、見過ごしたくないのに見過ごしてきたこととか、いろんなところで自分自身が負け続けて来た気がしていて。でも一度映画という形で残したら、それを守り続ける限り映画はそこに在り続けられるじゃないですか。僕らの“抗い”のようなものが社会の中で漂い続ける感じ。今の時代のなかで、この世の中に欠けているかもしれない何かを補填するものとして、映画ってすごく効率がいいんです。
ーーなるほど。髭野さんはどうですか?
髭野 自分は、仕事していても映画だし、疲れていても映画観ようかなってなるくらい結構映画が好きなので、映画が無いとちょっと困るなって感じです(笑)。でも、渡邉さんの言っていることもわかります。
渡邉 もちろんそれだけじゃなくて、考えたことが無いようなことにどっぷりと浸かって、そのことを考えてしまうというのも映画の魅力ですよね。個人的には、映画はいろんな意味で効率の良い体験をもたらしてくれると思っています。なので、自分が作るなら映画じゃないとできないことをやっていきたいですね。
ーー「なんで映画なのか」という質問良いですね。以前は「映画が好き」ということは個人の1つのアイデンティティとして語れるものだったけど、最近その感覚も変わってきている気がするんですよね。更に奥にあるものが重要になってきているというか…。
渡邉 いつからか「映画が好き」というカルチャー装備はそれだけでは何の意味も無くなってきている気がしていて。趣味は映画鑑賞です、みたいな。「何の作品が好きですか?」とか「なんでその作品が好きなんですか?」みたいなところまで語れないと、そのカルチャー装着はできないようになってきているなって思うんです。
ーーそれはなぜでしょう?
渡邉 社会がざっくりしなくなったからではないかなと思います。社会も文化も細かくカテゴライズが進んでいますよね。社会問題も今すごくカテゴライズされた先の問題がちらばって並存している感じになっていて。だから、社会現象的にヒットするドキュメンタリー作品もどんどん少なくなってきている気がします。
ーーザックリとした世の中と、いろいろカテゴライズされた世の中だったら、映画づくりの環境としてはどちらの方が作りやすいと思いますか?
髭野 プロデューサーとしていうと、今年来年は映画を作りやすい環境では無いですよね。なので無理して映画を作ろうという気持ちにはならなくて。このタイミングで出会えた方とか、いろんな御縁や機会から映画を作れています。自分は映画を作ることそのものを仕事にしているタイプではないので、とにかく映画を作らなければいけない、というところからは一歩引いてしまっている感じがあるかも知れません。
渡邉 そもそも、映画業界のある規模以下は産業であるとは言いづらい状況があって。そこで映画作りをしているプロデューサーが、映画を作り続けないといけないというのは矛盾しているのかもしれません。ある人がインディペンデント映画は「誰にも頼まれていないけれど作る映画」といっていたのを覚えているのですが、システマチックに作れないのになぜか商業映画と並べて語られることもあるのがインディペンデント映画なんです。
髭野 インディペンデントの立場では、予算や枠が決まっていて作らなければいけないわけではないから、毎回どういう形で映画を作るかを都度考えていかなければならないし、同じやり方で続けていけるわけでもないですよね。
ーー企画のしやすさで言ったらどうですか?
渡邉 僕の視点からすると、映画が産業的に作られやすいかということと、個別的に作られやすいかというのは、ちょっと視点が違っていると思っていて。それをお金が集まりやすいか、認めるべき企画が出てきやすいかと言い換えるとすれば、後者の方は今すごく作られやすい時代だと思います。
細かくカテゴライズされた世界では、作り手が、どの時点で、どの場所にいるか、どんな過去を持っているかの掛け合わせがそのままオリジナリティになりうるからです。ある趣向をもった“私”がたまたま“そこ”に“その時”居たことが企画として立ち上がりやすい時代にはなっているのではないかと思います。
PROFILE
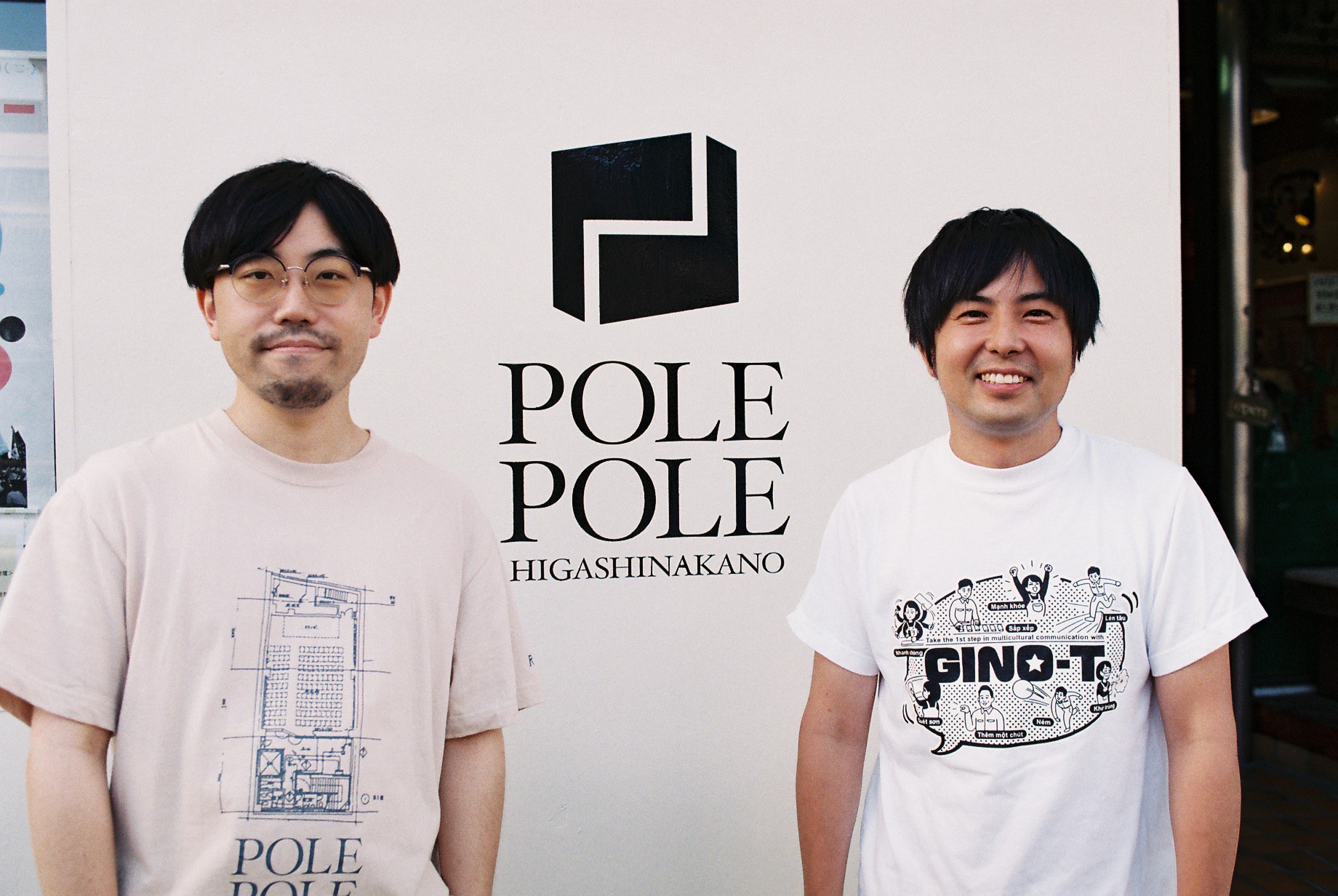
写真左:髭野純プロデューサー、写真右:渡邉一孝プロデューサー
渡邉 一孝(わたなべ かずたか)
1986年生まれ、福井県出身。配給会社、俳優事務所、映画祭のスタッフを経て、日英翻訳のコーディネートや映像字幕制作、自主映画の制作を行う。2014年に映画の企画から配給/セールスおよび翻訳字幕制作を行う株式会社E.x.N(エクスン)を設立。製作/プロデュース作に『黒い暴動♥』(16/宇賀那健一監督)、藤元明緒監督作『僕の帰る場所』(17/日本=ミャンマー)、短編『白骨街道』(20/日本=ミャンマー)、『海辺の彼女たち』(20/日本=ベトナム)。山形国際ドキュメンタリー映画祭ラフカット!部門のプログラムコーディネーター。映像を観て対話する「見たことないモノを観てみる会」を主宰。
髭野 純(ひげの じゅん)
1988年生まれ、東京都出身。合同会社イハフィルムズ代表。アニメ会社勤務を経て、インディペンデント映画の配給・宣伝業務に携わりながら、映画プロデューサーとして活動。配給を担当した作品に『ひかりの歌』(19/杉田協士監督)、主なプロデュース作品に『太陽を掴め』(16/中村祐太郎監督)、『もみの家』(20/坂本欣弘監督)など。『彼女来来』(山西竜矢監督)、『映画:フィッシュマンズ』(手嶋悠貴監督)が公開中。『春原さんのうた』(杉田協士監督)が2022年新春よりポレポレ東中野ほか公開予定。
映画『街の上で』公式サイト
『映画:フィッシュマンズ』公式サイト
